こんにちわ。わらびです。
まだまだ書くことはあるのだが、いまいちやる気が出ない。
久しぶりに過去の旅行の振り返りでもしようかなと思った次第。
そんなこんなで今回は、ルーマニアの廃村「ジャマナ村」について書こうと思った次第。
ジャマナ村とは?

トランシルヴァニアの奥地、アプセニ山脈の谷あいに「ジャマナ村」という小さな集落がありました。
けれども今、その場所は鉱山から流れ出す汚泥と汚水に沈み、地図の上から姿を消しています。
“かつてそこにあった村”
それが、いまの正しい呼び方です。
この村の悲劇は、銅の光に目を奪われたひとりの男の野心から始まりました。
その名は「ニコラエ・チャウシェスク」。かつてルーマニアを支配した独裁者として有名ですね。
第二次大戦後のルーマニアはソ連の衛星国でしたが、1960年代になるとチャウシェスクはソ連への依存を断ち切り、自立した社会主義国家を掲げました。
豊富な資源を活かした重工業こそが、その野望を支える柱となったのです。
意外と知られていませんが、実はルーマニアは、石油や天然ガス、石炭などが豊富なヨーロッパ有数の資源国。
なかでも銅は、電力を運び、工場を動かす国家発展の象徴とされました。
そんな折、ジャマナ村の近くで巨大な銅鉱床「ポイエニ銅山」が発見されます。
ヨーロッパでも有数の埋蔵量を誇るこの鉱山は、国家に莫大な利益をもたらす一方で、銅の精錬には有毒な鉱滓、毒を含んだ泥が必ず発生します。
それをどう処理するかは、環境と人々の命運を左右する問題ですが、利益が優先され、環境やそこに住む人々が蔑ろにされてしまうのが歴史の常。
当然、チャウシェスク政権も利益を最優先で開発を開始。山あいのジャマナ村にダムを造り沈め、その地を鉱滓の貯水池にしてしまったのです。
村人たちに支払われた立ち退きの補償金はわずか。
拒んだ村人の家は容赦なくブルドーザーに押し倒され、そのあとを追うように、毒を含んだ泥水が流れ込みました。
畑は覆われ、家々は埋まり、教会の鐘楼の半ばまで泥が迫る。やがて鐘の音は聞こえなくなり、静寂だけが残りました。
かつてここにあったのは、小さく美しい村。
灰色の土砂と赤い毒水に覆われた一帯が村だったことを示すのは、泥の中から突き出ている教会の尖塔だけ…
ルーマニア国内でも、環境破壊の象徴として有名で、観光ではありませんが足を運ぶ人も多い場所。外国のメディアが取材で行くには許可が必要みたいですけど、個人で行く分には問題がないので普通に行ってきました。
いざ、ジャマナ村へ

クルジュナポカを朝早くに出発しジャマナ村へ。
近くの村まではバスが出ているので、降りた後は2時間ほど山の中を歩きジャマナ村へと向かいます。

霧の立ち込める中、山道をひたすら進む。
埋まってしまったのはジャマナ村だけなので、周辺にはまだ人も住んでいます。
そこに住む人たちへの生活物資運搬車両やブルドーザーなどの工事用車両など。ここを通るのは重量級なので、未舗装路ではあるけど、かなりしっかりとしています。

村の近くについたのでそこで朝食タイム。
左からライスとミネストローネ、ルーマニアの伝統食ミティティ。
弁当箱が気になる方もいるでしょうが、これはフィリピンの人気ファストフード「Jollibee」のグッズ。
フィリピンで語学留学していた際に学校の先生から貰ったものです。

小さな教会の横で食べていました。
この教会は廃墟などではなく、今でも使われているのか手入れもしっかりとされているようでした。
今もジャマナ村に残って暮らす、数少ない村人のためのものでしょうか?
朝食も食べ終え、いよいよジャマナ村跡地へと向かいます。

季節は秋。
午前のまだ気温が低い時点では、山間部に流れ込んだ雲が滞留しホラーな雰囲気。
現在のジャマナ村のシンボルである、泥に埋もれた教会の尖塔もうっすらと見えます。
村にあった建築物は、殆どが泥の下。
この尖塔だけが、かつてここに村があったという数少ない証明となります。
冬であれば泥が凍り付くので、尖塔まで行けるみたいですが、それ以外の季節は流れ込んでくる汚染水で足場はゆるゆる状態。
私も泥濘にはまってしまい、買って間もない靴が泥まみれになってしまいました。
今回は泥濘程度で済みましたが、場所によっては底なし沼。場合によっては死ぬかもしれない危険な場所。

ジャマナ村は、鉱山側に近い方が有毒水の貯水池となっていて、鉱山から離れると土砂の堆積エリアになっています。
場所によっては足元がずぶずぶと沈み込み危険なのですが、牛なのかウマなのか分からない放牧動物の足跡が続いていたので、その安全と思われるラインをたどりながら、土砂の上を慎重に歩き進みました。

周囲には、鉱山から流れ込む不気味な色をした水の流れ。
数十メートル先には有毒とされる汚染水が広がっており、足元はひとまず大丈夫そうとはいえ、これ以上進むのはさすがに怖くて断念しました。
恐れおののいたのではなく、勇気ある撤退。ベトナム戦争のアメリカと同じです。


土砂が押し寄せた一帯でも、高台にあった家屋は完全には埋まらず、場所によっては一階の大半だけが土に飲み込まれた姿で残っています。

さらに鉱山側に近づくと、銅鉱山から流出した赤い有毒水がたまるエリアが見えてきます。
人が近づかないようにということなのか、周囲にはロープが張られ、立ち入り禁止を暗に示しているようでした。

汚染湖からは有毒ガスが発生している。
そんな噂もネット上では見かけます。
しかし実際には、この周辺には今も普通に民家があり、穀物を栽培している畑さえあります。干してある衣類を見るかぎり、子どもも日常を送っている様子でした。
ネットには「立ち入り禁止」「有毒ガス」など、ジャマナ村に関する真偽不明の話が数多く流れています。けれど、実際にこの地を歩いた身として言えるのは、それらの多くは当てにならないということ。
情報が少なく、しかも負の側面を持つ場所だけに、興味本位の噂が膨らむのは分かります。
ですが、実際の状況を知らないままに、ほとんど妄想のような情報を無責任に拡散するのだけは、やめていただきたいところである。

帰り際、朝来た時に滞留していた雲もすっかりと流れ、土砂に埋まった教会の尖塔が姿をあらわに。
今でこそこんな有様ですけど、鉱山開発の一件さえなければ、今も美しい村の姿がここにはあったのでしょう。
おわり
銅鉱山開発で泥に沈んだジャマナ村。
真偽不明の噂が先行しがちな場所だが、実際には、わずかながら人々の暮らしの気配も残り、過去と現在が静かに交錯しているそんな場所でした。
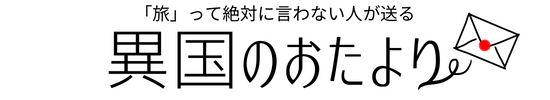







コメントを残す